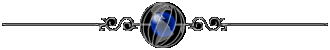
by くわはら智美
2.NIGHTMARE 悪夢
「…う…」
闇の中に、押し殺したうめきと、微かにべッドのスプリングのきしむ音、そして、荒く乱された息づかいが、うたかたの様に生まれては消えていく。
ユキの汗ばんだ肌が、開け放した窓から差し込む星明かりに浮かび上がっている。
不思議にアルフォンの青い肌は、保護色を身に纏っているかのように、闇に溶け込み、没し去っていた。
しかし、ユキの身体の上に確かにかかる重さが、嫌と云う程彼の存在を主張している。
あの夜、さすがに激しいユキの衰弱に、医師が禁止を言い渡してからは、アルフォンはユキの存在を忘れ去ったかの様に、このユキの病室に当てられた部屋を無視した。
医師と、時折訪れるあの女性の手厚い看護で、次第に身体も回復し、傷口もふさがった頃に、再びユキの悪夢は始まった。
ユキにとって二重に苦しいのは、いくらアルフォンの仕打ちを憎み、拒絶しようとしても、いざその悪夢が始まれば、身体は心を無視して、勝手に反応してしまうことだ。
「は…あ…」
声をあげまい、としても、事実身体中が快感に酔いしれている。
敵を、アルフォンを憎悪しているのに、もうひとつ、別の命を持つかの様に、悦びにうごめいている、自分の意のままにならぬ身体…。
前戯の終わる頃には、身体が、アルフォン自身を狂った様に求めている。
求めずにはいられなくなる程巧みな唇や舌の動きに比べて、体位はいつも同じで、力任せだ・・・と、あの女性
―――ゆかり、と名乗った。
「源氏名よ、姓は捨てた」・・・と―――
が、吐き捨てる様に去った言葉を思い出す。
そして、ユキも、己れから身体を開きこそしないが、早くアルフォンに、来て欲しい…と願っている。
さっさとすませてくれ・・・という投げやりな九十九%の心と・・・残りの一%の認めたくない真実は、この熱く燃えている身体の芯を鎮められるのは、自分をここまでおとしめてしまったあの男だけだ…。
心の中で血の涙を流し、古代に詫び続けながら、アルフォンのもたらす快感に身をゆだねいてる…この夜を楽しんでさえいると、自虐的にユキは考えることもある。
抵抗をしたところで結果が同じなら、受け流すしか無い…と判っていても、この嫌悪感、罪悪感は消せるものではない。
それがかえってユキの身体を燃え上がらせている。
熱い闇の中で身体を重ねあいながら、ユキにとっては、この空間は、甘い夢を紡ぎ、情事を楽しむどころか、壮絶で、絶望的な戦いの場でしかなかった。
「あぁ・・・」
熱い塊が秘処に押し当てられ、じわじわ…とユキの身体の奥に、鈍い痛みが伝わって来る。
毎夜の様にアルフォンは、ユキを抱く為だけにこの部屋を訪れていた。
無駄話などまるでしないのは、情報を漏らしてしまうことを警戒してか、身体以外に目的など無い事をユキに思い知らせる為か…。
もっとも、ユキにしたところで、言葉を交す気などかけらも無いのは事実だが、情報、という点では、アルフォンの無口を残念にも思っていた。
痛みが、次第に熱い波に変わっていく。
しかし、その夜のアルフォンは、いつもの、ただの義務感から抱いているという雰囲気すらある性急さを見せず、いつまでたっても、クライマックスへの動きを始めなかった。
不審に思って固く閉じていた瞳をわずかにあけて様子を見たユキは、腕を立てて自分を冷ややかに見下ろしているアルフォンの瞳に、自分への嘲りを見つけた。
じらされている。
思わず、恥辱に憤り、目をそらす。
いつも、感情を必死で抑え込もうとし、決して自分の言いなりに溺れないユキを、乱してやりたい…。
アルフォンの瞳は、そう云っていた。
やがて、不意にアルフォンが、激しく動き始めた。
突き上げる様な衝動がユキの身体を襲う。
身体が自然にずり上がるが、頭がベッドの上部にぶつかり、すぐに逃げ場を失ってしまう。
「あうっ……うっ…」
噛みしめられていた唇が微かに開き、アルフォンの動きの度に漏れるうめき声は、次第に熟を帯びて来る。
からみあう獣…とは表現出来ない姿だった。
ユキはいつも、出来る限りアルフォンから遠ざかろうと身体をそらし、手はシーツを握りしめている。
アルフォンも、前戯の時はともかく、自身でユキを貫く時は、今と同様、腕を立てて、ユキを観察するかのごとく見下ろしていた。
かえって、繋がりあった部分だけに感覚が集中し、相手を深く感じあうことになる、が、アルフォンの無機質な肌に触れる部分が最小限ですむ方が、ユキには歓迎出来た。
しかし、今夜は思いの他の激しさに、無意識のうちに、手が、アルフォンの腕を求めてしまう。
「あ…あぁっ…」
唾液が一筋、流れ出た。
熱に浮かされた様にうめき、喘ぎ続けるユキは、次第にアルフォンの背に手を回す。
それに応えてアルフォンが、少しずつ身体を重ねていく。
口許には、征服者の残忍で満足気な笑みが浮かんでいた。
たわいもない…。
これが女というものか…。
もう少し抵抗して、自分を楽しませてもらいたいものだ、などと勝手なことを考えるアルフォンは、完全にユキを抱き締め、からみあい、絶頂へ向けてかけあがろうとした時、腕の中の獲物が反撃に転じたのを知った。
長い間手入れもしていなかったユキの爪が、アルフォンの背に突き立った。
皮膚を切り裂き、深くえぐった感覚がある。
次の瞬間、頬を張り倒されたユキの身体は、ベッドの下に落ちていた。
床で強かに頭を打ちつけたが、気を失う暇も無く、再びアルフォンの腕で乱暴にべッドに引き戻される。
「小賢しい真似をしてくれる…」
いつも冷たく輝き、時に冷笑を浮かべるだけのアルフォンの瞳に、明らかに怒りと、残虐さを含んだ愉悦の色が見てとれた。
どのように辱めようと、いつも毅然と自分を見返して来るこの女…。
媚びを売ることも、許しを請う事も全くしようとせず、思えば一度も自分に対して口を開いていない。
情事の最中の微かな喘ぎだけが、アルフォンが耳にしたユキの声の全てだった。
この挑戦的な睦を持つ女を、跪かせてみたい…。
ユキの初めての抵抗が、アルフォンの嗜虐の心に火をつけた。
「じゃじゃ馬ならばこそ、乗りこなし甲斐もあるが…少々、調教し直す必要があるようだな…」
「あああっ!」
言葉と共に、ユキの両肩をつかんだアルフォンの腕には、少しずつ力が加えられていく。
塞がりかけた傷口からまた鮮血がにじみ出し、気を失うことも許されない痛みにのけぞるユキの口からは、細く鋭い叫びが初めてこぼれる。
血の色に逆上したかの様なアルフォンは、暴力でなく、ユキを最も傷つける方法で嬲り始める。
…抵抗はするまい。
そう思っていたはずだったユキだが、のぽりつめていく感覚の中で、このままでは自分はこの男に負ける…とひとかけら残っていた理性が叫んだ時、思わずとってしまった行動だった。
が、その結果がこれだ。
滅多な事では感情を見せないアルフォンをここまでムキにさせては、ただでは済むまい。
自業自得とは云え、肩の新たな痛みは、鼓動に合わせて疼きが襲いかかり、アルフォンの仕打ちを心配する余裕も無い。
「…あれだけ悦んでおいて、つれないことだな…」
心をえぐっていくはずの言葉も、再び自分の身体を轟き始めたアルフォンの指も、痛みが消していく…。
「…心を許さなければ堕ちては…自分が汚れていないとでも思っているのか」
乳房を這いまわる唇から漏れた、蔑みだけで形作られた言葉に、痛みを捩じ伏せて薄く目を開けたユキは、軽く笑って見せた。
自嘲の笑みでも、アルフォンへ向けられた侮蔑の冷笑でもない、無垢な少女の様な、儚く、しかし鮮やかな微笑みだった。
ユキの、思いもよらない反応に、躊躇したアルフォンは、その一瞬をついたユキの次の行動に反応しそこなってしまった。
「うあっ…」
動かせる方の右手が、今の様子からは信じられ無い程の動きを見せ、今度は思い切り頬を引っ掻いたユキは、先程とは打って変わって口の片端だけを上げた、相手を思い切り馬鹿にし、小悪魔めいた微笑みを浮かべた。
年齢に不釣り合いとも思えるそれは、自虐気味な心に苛まれ続けた日々が、彼女に身につけさせた種類の表情だろうか…。
これが、ユキを崇拝する男であったなら、足もとに跪きかねない程に、相手を轟惑する力を秘めていた。
きれいに並んだ鋭い傷は、相当に深いらしく、赤いものが流れ、首筋を伝い落ちる。
アルフォンは、またもやユキの表情に息を飲んでしまった自分への怒りをまたユキへ向け、再びユキの身体は床へと落下する。
意識を失った訳ではないが、動く気力はさすがに尽きたユキを、アルフォンは何度もそのまま床の上で責め立て続けた。
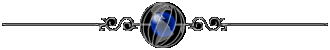
「―――少尉」
接収して、前線本部にあてられた建物の長い廊下に、野太い声が響いた。
…嫌な相手に呼び止められた…と、一瞬しかめた表情を元に戻してから、アルフォンは声の主の方を振り返った。
上官の大尉が、妙に機嫌良く、独特の精力的な大股で近づいて来る。
嫌っている訳でも、苦手としている訳でもないが、タイミングが余りに…自分にとってみっともないという自覚が、僅かにアルフォンを受け身にさせる。
昨夜、ユキの残した頬の傷の手当の為に張られた医療用パッドは肌の色に合わせてあるとは云え、余り名誉とも云えぬ負傷の存在を明らかに周囲へ主張していた。
自分より下位の者には、有無を云わせぬ眼光で黙り込ませ、耳に人らない所での密かな噂話に抑えつけられるが(罰して取り締まるなどという大人げない振舞いはしたくもないが、自分の耳に入って来るのが煩わしいのだ)上官ではそうもいかない、という訳だ。
「ほう…これが、朝からの不穏な空気の原因か」
大尉にまで噂が届いていた訳か。
余程度胸のある奴がいたものだ、とアルフォンは苦笑する。
この、アルフォンの傷を笑った相手も、ほぼ同じ位置にパッドを貼っているのだ。
もう治りかけて小さくなっているその跡をつけた女が、新しい傷をつけた女と知りあっている…などということは、この男達は知る由も無い。
特に女姓達が秘密にしている訳ではないが、アルフォン達が全く獲物のプライバシーに興味を持っていないだけの事である。
「少尉のパートナーは、確か重傷を負っていた…と問いたが…」
ここで、ひどく愉快そうな笑みを浮かべる。
「何を物好きな…と思っていたが、成程、面白そうな相手だ」
バン!とアルフォンの背を叩き、豪放、としか表現しようのない声で笑う。
―――自分の趣味と一緒にしないでくれ…と、頭痛を覚えそうなアルフォンは、ひたすら苦笑を続けるしかない。
この上官は、自分に反抗し、引っ掻き、噛みついた威勢の良さが気に入って、ずっとその女を手元に置いていると聞いた。
一人の女を相手にしているのは、この任務を言い渡された数十人のうち、自分とこの上官の他、全体の三分の一程を占めていた。
…そう、全ては任務なのだ、と、ひどく叩かれても痛みひとつ感じないもうひとつの傷口の事を思い、苦笑が自嘲の笑みに変化する。
サイボーグである体幹の傷は、放置しても悪化もしないかわりに治癒もしない。
見栄えが良くないから直そうとは思っているが…当分あの女を抱くこともあるまい。
生身の身体を欲しがった連中とは、一体、どこのどいつだろうか…。
少なくとも、自分の周囲にはほとんど存在していない。
ムードに浮かされて生身の身体への憧れを口にするものもいたが、自分達兵士にはサイボーグの方がなにかと便利であるのは一目瞭然である。
案外、上層部のノスタルジックな感傷のせいで、こんな大がかりな作戦を命じられたのかも知れない…と、底意地の悪い声も密かに前線の兵の間には、決して高くはならないが、消えることも無く語り継がれていた。
欲しがるくせに臆病なものだから、自分達が実際に手に入れる迄に、色々とデータを欲しがる。
メリット、デメリットの計算は、大総統が作戦に対する命を下す前にされ尽くしていた。
生身の身体の最大の敵の病気や事故(これが理由で、その身体を捨てたはずだった)も、今の科学力では難なく克服出来よう。
…それに、地球人の身体の方が、母星の失われた身体より強靭なようで、自分達にとって致命的な病も、たいした害にならないとは、憧れても不思議は無いだろう。
老化防止の策もサイボーグ化の段階で問題はなくなっていた。
…だから自分達は半ば永遠の生命を手に入れでいるのだ。
何を好き好んで・・・という気持ちをアルフォンが抱いても不思議はあるまい。
上層部が怖じ気づく最大の事柄は、サイボーグには無縁の、生殖活動について…だった。
まさか、母胎で子供を…などという野蛮な行為迄復活させるつもりはあるまいが(出生率の低下と、性生活によってのみ感染する疫病の蔓延が、人工子宮、そして機械造りの身体へのきっかけであったことは誰でも承知している)、手に入れれば、昔話に聞き続けたものを体験して見たくなるのも、自然の成り行き…というものだった。
しかし、その行為が、ただ一つだけ残った本物の自前の身体である『頭脳』に与える影響が心配だったらしく、アルフォン達の部隊を選びだし、文献だけを頼りに生殖器に限り無く近付けた機能を持たせる為に改造を施し、征服したこの地球で、女を征服する任務を与える・・・など笑い話でしかないではないか?
同僚達は、適当な女を見つくろって、楽しんでいた。
提出される報告書も、脳に与える刺激は恐れたりする必要は無く、大変心地好い種類のものだ…と肯定しているものが殆どだった。
アルフォンは、どうしてもその気になれず、気に入った女が負傷しているという事を『任務』に取りかからない云い訳にしていたのだ。
細かいことに頓着しない上官は、半分拒否している様なアルフォンの態度も大して気にもかけていなかった。
『やってみれば判る』とでも云う様に…。
ただの任務、スポーツだとでも割り切っているのか、同僚達は、凌辱した相手が絶望の余り自殺をはかったり、狂気に逃避しても気にもとめず、新しい相手に乗り換えるだけだった。
余りに目に余る媚態を見せる女というものもいただけないのか、気楽さから商売女を相手に選んだ者の方がよく女を取り替えていたようだ。
…その点では、抵抗する方が面白い…という上官の趣味は、誰もが持っている…という訳であろうか。
ただ、、『犠牲者』として選び出された地球の女達は、それぞれ任務を帯びた将校達一人一人の囲い者になっているので、大昔、地球人が同じ種族の女運に働いた『従軍慰安婦』などというひどい行いよりは、はるかにましではなかろうか?…とアルフォンなどは考える事がある。
何人もの男達に寝る間もなく拾姦される事は、少なくともない。
…不思議に、この任務を嫌がり、拒否する者はいない。
気乗りしなかったアルフォンですら、何度ユキを抱いたか数える事など出来なくなっていた。
…人間の本能…という訳か。
地球人の女達についての品定めのついでに母星に残る自分達の同種族の女達の『テストケース』がやって来るので、今度は地球の男を狩る必要がある…などと噂している仲間達を、醒めた目で突き放してながめるアルフォンだった。
哀れではないか? 機械の身体で最も大切なものを踏み瀾られ、慰みものにされているあの女達も、作りものの快感に満足している自分達も…。
アルフォンは、今では、自分が生身の身体を手に入れる事を望み始めていた。
…体温を機械に作り出してもらわねば不審に思われずに握手さえ出来ないこの身体ではなく、あの女と同じ身体で、生暖かく、グロテスクで粘液質な物体として、白く、滑らかな肌をからめとってみたかった…。
痛みも、苦しみも、快感も、その胸に抱く地獄も…なめつくしてやりたかった。
惑わされはじめているのかも知れない…。
冷徹と謳われた表情は崩す事なく、単純そのものの上官をあしらいながら、自分の心の中の闇をのぞき込み、感じる事のないはずの寒気と、正反対の熱い昂ぶりを同時に覚えたアルフォンは、軽く、閉じた目頭を押さえた。
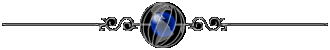
「無茶をする・・・」
医師の、そろそろユキの性格をつかんだのか的確な表現に苦笑したユキは、つぎの瞬間、痛みに顔をしかめた。
肩に受けた傷は、自分の努力を何と思っているのか再び悪化させる。
身体中に新たな打撲や擦過傷を作ってくれる。
…肋骨にはひびが入っているではないか?
この患者は、自分の身体を何と心得ているのか、と、嘆きたくなっても仕方あるまい。
諦観から、敵の言いなりになっている女性ではない事は判っていた。
耐え忍ぶには余りに辛い仕打ちにさらされていることも。
しかし、だからこそ、自重して欲しい、せめてこの深手が癒える迄位は。
…それ位は、自分の身体を大事にしても罰は当たるまいに、恋人を裏切らされ、辱めを受けておめおめと生き延びている自分への憤りからか…ことさら修羅の中に身を置きたがっている様な姿に、医師は心を痛めていた。
もう少し、心をなくせば、楽になれるだろうに…と。
何の力にもなれない自分の不甲斐無さへの怒りの為か、多少治療が乱暴になってしまったようだ。
もっとも、これくらいで応える相手でもあるまいが…。
「…先生は、外科が専門、でしたね…」
「切れた唇に薬を塗っている時くらい、黙っていなさい」
初めて治療した頃に比べ、格段に心の平静を取り戻して来ていたユキと、気軽に言葉を交せる迄に信頼関係を作れたことは、数少ない喜びである。
医師の言葉に大人しく従ったユキは、治療が、アルフォンが身体中に残していった傷跡の方へ移ってから、改めて口を開いた。
「後で爪切り、取ってもらえます?」
「ん?」
見れば、ひどく汚れている。
仕方あるまい。
平素なら美しく手入れされて然るべき、細く長い指が…。
そういえば、確かその指に輝いていたはずのエンゲージリングは…。
やはり、深すぎる心の傷が、それを目にする事を拒んでいるのか見当らない。
「…昨夜、アルフォン少尉の身体を、思い切り引っ掻いてみました。皮膚の組織片が詰まっているはずです」
自分の汚れた爪を眺めながら、ぼんやりと呟く様に、静かに言葉をつぐ。
「…背中を…。右手には顔の皮膚も。分析する手段はありませんか?」
何事かといぶかる医師を、ユキはあくまでも静かな睦でのぞき込み、また少し声を低くする。
「不思議…だったんです。アルフォン少尉達の性欲は…唐突過ぎるんじゃないか…って」
『まるでスイッチを入れでもするみたいに、いきなり始まって、突然終わるんだから』
これは、ゆかりに云われて初めて気づいたことだが、アルフォンにも確かに感じられた。
占領地の女を収穫品として楽しむというより、研究対象として、自分達自身の反応を調べているかの様な姿が…つくりものめいて感じられた。
腕を立て見下ろすのも、肌を重ね合わせるのを避ける為の体位…とも推測出来る。
額には確かに光るものがあり、汗の雫がこちらの顔に落ちることもあるのに、体臭というものをほとんど感じさせない身体は…。
頭部にだけ汗をかく体質か…とも考えたが、まさか、自分達をこれ程までなぶりものに出来る連中の身体が、地球人と大きな違いを持つとは考えにくい。
アルフォンに身体を貫かれ、噂ぎ苦しんでいる最中にも、意外に醒めている心の中―――必死で抵抗して、引きずり込まれないように抗っている為だろうか―――を、ふと漏らしたゆかりの言葉がかすめた時、ひとつの計算が働いた事は、アルフォンに知られてはならない。
だから二度もアルフォンに爪を立てた訳だが、頬を伝う血を見た時、失望を感じた。
しかし、その後、冷静に考えてみて、二個所の細胞を得た事は、かえって幸運だったのかも知れない、と思っていた。
ひとつの仮定がユキの中で生まれていた。
医師は、か細く、頼りなげな身体を意志の力で支え、自分の武器で立ち向かおうとしているユキの姿に、畏敬の念すら抱いていた。
とうの昔に捨て去った、地球人類の希望が、ユキの身体を形作っているかに思える。
楽になれる道を選ぶことを己れに禁じているこの女性の精神力…その源は一体何なのだろうか。
強い意志を見せれば見せる程、危うくも感じてしまう。
切れることなく張り詰め続けられるだろうか。
悪夢の中で、美しく、艶やかに咲き誇る花は、血の色にも染まらず、あくまでも白い