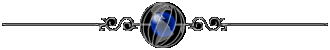
by くわはら智美
1.Labyrinth
悪夢の始まりは、予想外に早かった。
連絡艇発進の際、負傷して地球に取り残されたユキが、敵の将校に救われた事を知らされて一週間目。
ようやく肩の傷が原因の発熱も峠を越し、おさまりかけていた。
ずっと、ぼうっとした夢うつつの世界にいたので、気がついてから一週間、という判断は何とか出来たが、どれくらい気を失っていたか…は、まだ確認する術を持たなかったユキは、夢の中で何度もうなされ続けた現実を、しっかり見据える作業から始めようとしていた。
肩の痛みより激しく自分を苛み、熟にうかされた自分の眠りを何度も引き裂いた、一つの悪夢…。
アルフォンと名乗ったこの屋敷の主は、連絡艇の生命反応が消えていたと告げた。
古代達が死んだという事に他ならないそれは、ユキから、怪我の回復に必要なやすらかな眠りを奪った。
信じたくないと心が叫び、熱に加えて悪夢が体力を奪い続ける。
アルフォンが呼び寄せた初老の地球人の医師は、真剣にユキの治療に取り組まねばならなかった。
そして、むりやり占領軍に協力させられているその医師は、この、傷ついた美しい女性を待ち受けているであろう悲劇に、心を痛めていた。
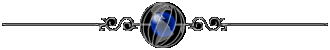
そして、その夜、ユキの病状もようやく安定し、ゆっくりだが快方に向かうだろうと告げられたアルフォンは、いつもの通り、面白くもなさそう…と云うより、冷ややかにそれを聞き流し、医師を下がらせた。
「…そろそろ…か。いつまでも遊ばせておく訳にもいくまい」
手にしたグラスを目の高さまで持ち上げ、のぞき込みながら、一人つぶやく。
聞く者は誰もいない、自分自身へ向けたその言葉には、これから自分が行おうとしている事への昂ぶりは全くうかがえず、ただ義務感に重い腰を上げようか、という口ぶりだった。
そして、ユキにとっての、もう一つの悪夢が始まろうとしていた。
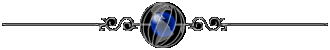
寝汗の不快さに目が醒めたユキは、傍らに立ち、自分を見下ろしているアルフォンに気づいた。
医師とアルフォンの他、この部屋に入って来る者はいない。
医師ならば、どんなに深く眠っていても気配で目が覚めた。
悪夢を中断してくれたことも度々で、同じ地球人として、アルフォンよりははるかに歓迎出来る人間だったが、全く気配を感じさせないアルフォンは、彼が敵である、という事以上にその無機質なイメージに恐怖を覚えていた。
防衛軍一、二を争う美貌と謳われる彼女である。
男達の遠慮の無い視線にさらされた経験も多い。
が、アルフォンのその視線は、自分の身体にはりつき、まとわりつくのはその男達と同じなのに、全く熱を感じさせなかった。
なめまわす様ないやらしさと正反対の、まるでスキャンでもしているかの様な無感動な瞳を向けられる方が、より、ユキの身体に起こる震えは大きかった。
「…『古代』とは、恋人の名か」
やがてアルフォンが口にした言葉は、ユキの心を遠慮無くえぐった。
質問ではない。
ユキの身元も、軍内に婚約者がいた事も既に調査済みである。
しかし、うなされている彼女が何度も口にした名前を、これから自分がやろうとしている事の前に彼女に聞かせるのは、不思議に、嗜虐な喜びをアルフォンにもたらした。
やはり、未開の人種を相手にすると、変わった精神的経験が出来るものだ…と、アルフォンは苦笑に似た気分になる。
この星と自分の母星の、最大の違いは、文明の発達の度合いでも、ましてや生身と機械の身体の差でもない。
人々の抱く感情というものの多種多様さ、であるな、と。
そして、正しく自分は、そういったものを報告する役目を負っているのである。
古代の名は、ユキの心を目の前の現実から背けさせ、彼女を無防備にした。
…そして、アルフォンには、一瞬のスキで充分だった。
気がついた時には、ユキは、アルフォンに抱きすくめられ、身体の自由を奪われていた。
「な…!」
ついで、唇も奪われる。
その気になれば、同時にやってのけられるであろう事を、わざとずらせたのは、ユキに悲鳴をあげさせる為か…。
アルフォンの己れに対するいたぶりを感じて、ユキは、すんでのところで迸りそうになった叫びをこらえた。
覚悟は、していたはずだ。
こんな形で生き延びてしまった。
そして、古代達の生死はまだはっきりしていない。
たとえ死んだとはっきり告げられたとしても、この目で確かめる迄は信じられるものか、という信念。
信じたくない、という悲痛な想い。
自分もヤマトの戦士の一人だというプライド。
それらがユキから、一番楽な逃げ道をふさいでいた。
―――ならば、これは通らざるを得ない関門なのだ。
せめて、誇りだけは失わずにいたい。
それだけがユキの願いだった。
力でははるかに相手が勝るのは試してみるまでもない。
その上、自分は、今は負傷し、体力を使い果たしている。
無駄な抗いは止めた方が利口だ・・・と判ってはいるが、初めて触れる古代以外の男性の肌は、ユキに生理的嫌悪感を抱かせるに充分だった。
気の進まない事は手早くすませたい…とばかりにアルフォンは、ユキのネグリジェに続いて下着まで、無造作に引き裂いていく。
ユキの代わりに布地が、細く高い悲鳴を上げた。
灯りの下で、一糸纏わぬ姿にされた蓋恥に身を固くしたユキは、日を閉じ、唇を噛み、必死に耐えていた。
自由になった口から悲鳴が漏れないという事を確認したアルフォンが浮かべた薄い笑いも、気づかない。
「…助けを求めても無駄…という訳か」
諦観と云うより、覚悟を決めたのか…とアルフォンは冷たく判断する。
女にしては見上げた精神力だ…と。
ならば、いやでも許しを請わせてやりたくなる…。
自分は、この星の風土に犯されかけているのかも知れない。
しかし、その危うさはアルフォンに心地よかった。
顔を背けているユキの身体が、びくっと小刻みに震え、硬直した。
アルフォンが、その、白くなめらかな乳房に唇をはわせ始めたのだ。
右腕はしっかり抑えつけられ、負傷した左腕はもとから力を入れられるはずも無い。
アルフォンは空いている自分の右手で、小さく、淡く色付いた乳首を弄び、同時にもう片方のそれに口付け、愛撫を始めた。
身体は正直だ・・・と、流れ落ちる涙を止める術を持たないユキは思う。
こんな相手でも、快感に反応し始めている…と。
処女では、なかった。
古代とほ既に何度も身体を重ねている。
最愛のその人とは、肌も髪も、腕の太さも、身体の重さも…愛撫の仕方も違うこの男とでも、自分は、悦びの声をあげてしまうのだろうか?
…最後のプライドとして、それだけは自分に許せないユキは、アルフォンに、古代にだけ許した場所を侵略された時も、唇を噛み、叫びを、そしてあえぎを漏らすのを必死でこらえていた。
思考がまとまらない。
身体は燃えさかり、反対に頭の中は血が引いていく。
傷がまた開いた感覚がある。
白濁していく意識の中でユキは、自分の中で猛り狂うアルフォンの確かな存在と、もう自分には古代に救いを求める資格はなくなったということを思い知らされていた。
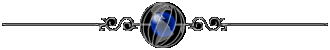
優しく、遠慮がちに身体に触れる手で、ユキは深く沈み込んでいた意識を浮上させられた。
目の前には、いつもの医師の心配げな顔があった。
気絶したユキを、ことのあとそのままに打ち捨てたアルフォンの姿は既に屋敷に無く、定刻に往診に来た医師は、惨い仕打ちに心を痛めながらも、ユキにシーツを着せ、起こさないようにそっと治療を始めていた。
妙な気を起こそうとすれば、家族が無事ではない。
口に出して言い渡された事ではないが、ユキを閉じ込めるという意志をアルフォンが見せている以上、自明の理である。
鍵を渡され、自由にこの家に出入り出来る医師には、ユキを解放してやる自由だけは持たされていなかった。
と、同時に、肩の傷はいくらでも治せようが…。
包帯で食い止めきれなかった血は、シーツの肩の辺りに、手折られ、無造作に投げ捨てられたような赤い花を形作っていた。
夢も見ない深い眠りは、今のユキにとって唯一の救いである。
それが判っているから精一杯気づかってみせたが、体力と気力を使い果たしたユキは、だからこそ神経を過敏なほどにささくれ立たせていたのだ。
医師の瞳に浮かぶ哀れみの色で、一気に昨夜の記憶が蘇って来た。
それをこの医師に知られ、同情を受けている事が、ユキの受けた傷を拡げる。
動かせる方の手で顔を覆いかけたユキは、手首にくっきりと、アルフォンの残していった跡を見つけ、泣く気力すら奪われて、打ちのめされてしまった。
痛みすら感じているのかいないのか、人形の様な虚ろな目を天井に向けたまま、ユキは、医師のなすがままに任せていた。
そうだ、今は全てを忘れるか、それが叶わなければ何も考えないことしか、この女性の心を守る術は無いと、心の中で深いため息をつきながら医師は考えた。
この女性の顔にも、時折うなされて呼ぶ名前にも覚えがあった。
まだ少女と呼んでも差し支えない頃に、地球を救う立派な働きをしたあの女性だということは、引退した軍医である彼には、知りたくも無いのに判ってしまった事実であった。
一緒に戦った仲間の一人と婚約していたはずの彼女が、こうして一人、翼をもがれて血の海でもがき苦しんでいるのに、差し伸べられるべき手は、失われて無い。
―――連絡艇の件は、傍らで聞かされていた。
地球の未来に対する絶望を象徴しているかの様なこの姿に、慰めの言葉をかけることも出来ない自分がもどかしく、逃げる様に医師は部屋を出た。
これ以上彼女の姿を見るのは、とてもいたたまれない。
しかし、起き上がる気力も無い彼女をそのままにしてはおけなかった。
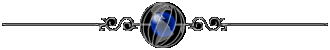
どれくらい時間がたったか―――
そっと足音を忍ばせて入って来る人影があった。
普段のユキなら聞き逃すはずも無い足音も、マヒした心には届かないようだった。
聞こえてはいただろう。
だが、それがアルフォンであろうと、あの医師であろうと、ユキにはもう、どうでも良かった。
いや、どうでもいいという意識すらしなかった。
身動きする気も起きない程に、深く打ちのめされていた。
しかし、固く絞られた冷たいタオルを顔に当てられ、ユキの意識は嫌でも現実に引き戻された。
のろのろと視線を動かすと、全く見知らぬ若い女性の顔があった。
ユキと同年代か、少し年上であろうか。
背格好や髪の色、長さは、ユキと良く似通っていたが、全く違った印象を受けるのは、派手で鮮やかな化粧と衣装が良く似合っているせいだろうか。
無言のまま、手慣れてはいないが、てきぱきとした動作でその女性は、顔から首筋、身体を拭いていく。
負傷して以来、身体を清めてもらうのは思えばこれが初めてだった。
気をつけてはいるが、時々傷に障る動きで痛みが走る。
「…う・・・」
止まっていたかの様なユキの時間が、次第に動き出す。
他人に汚れた身を始末してもらう羞恥も、一気に蘇り、ひとりでに涙がこぼれ落ちた。
そんなユキに、同情は余り見せず、事務的に作業を進めるのは、この女性の優しさであろうか。
声を押し殺して泣き続けるユキに、何とか服を着せ終わった彼女は、初めて瞳に同情の色を浮かべた。
顔を背けているユキの白いうなじを眺めながら、しばし考え込み、ためらった末に、女性のユキに対する哀れみが形になった。
ユキの、無事な方の肩に優しく手を置いたのだ。
びくっと振り返るユキの怯えた視線を受け止めた女性の表情は、聖母の様な、とか、慈愛に満ちたと迄は表現出来ないだろうが、充分に人間的な優しさがあった。
それが、ユキの限界だった。
激しく堰を切った様に涙があふれ、声をあげて泣き出した。
ずっと誰かに甘えたかった。
同情でも何でもいいから、自分に何もかも忘れてただ泣く事を許してくれる人が欲しかった。
アルフォンに対して、精神力の全てを使い抵抗し続けたユキに、これは救いの手にも等しかった。
すがりついて泣き続けるユキを、見知らぬ女性は優しく、気の毒な同性に対する同情以上のものを秘めた睦で包み込んでいた。
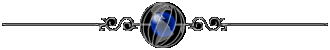
しばらくして、ユキがどうやら落ちついたらしい事を確かめた女性は、そっと部屋を出て行こうとした。
気づいたユキは、慌てて呼び止めようと声をかける。
自分のこんな姿を見られた相手だから、一刻も早く視界から姿を消して欲しいという気持ちも確かにある。
しかしそれ以上に、会話に飢えていたらしい。
最初に漏れた「あの…」という言葉は殆ど無意識だったが、後はまだここにいて欲しいという思いから言葉を継いだ。
「…すみませんでした、取り乱してしまって。お世話になりながら、お礼も云わず…」
呼び止められた女性は目と耳を疑った。
まさか、あそこまで自分を失っていたユキが、こんな短時間でまともな思考力を回復するとは信じ難い思いだった。
詳しい経緯は判らないが、深く愛しあう男性と引き裂かれ、地球を血に染めた敵の手に堕ち、慰みものにされた…その事自体は今の地球には珍しくないパターンだろうと想像出来る。
しかし、泣き叫び抗い続ける者、割り切って、もしくは諦めて相手に従う者、己れの心を失ってしまう者…それらの姿は想像出来ても、この、目の前の傷ついた女性の様な、自分をしっかり持ったまま立ち直ろうとしている姿は、心底意外だった。
(まだまだ地球人も、ヤケになっちゃいけない…ってことですか)
同情していたはずの相手に心の持ち方を教えられるなんて…と、ふと、苦笑が漏れる。
「あの・・・あなたは?」
「あ、内藤さん…って云っても判らないか、あのお医者に頼まれたの。近所のもんだよ」
近所の…と云われても、占領下の地球人に、他人の、しかも占領軍が接収した家に出入りする自由が与えられているのだろうか、と、ユキは途惑う。
急襲の夜以来、このベッドに釘付けの自分には、現在の地球の状況は全く判らなかったが、常識では納得し難い。
ユキの困惑を見て、女性は、自嘲の混じった少し淋しい笑みを浮かべる。
「あたしは、初めての時に抵抗して張り倒されたケガで、内藤サンのお世話になってんの」
と、前髪に隠れていた傷を見せる。
額を何針か縫っているらしい。
「え…」
「あんたと同じだよ」
思わず息をのむ。
自分一人が苦しんでいる訳ではない、というし事は理解しているし、それを己れへの叱咤の拠り所にもしていた。
気力を失いかけると、すぐに悲劇の主人公の気分になってしまう…と。
だが、こうしてたいして事もなげな様子で、自分も敵兵の性欲の処理の道具にされている…と云ってのける女性がいるとは…。
決して、厚顔無恥で羞恥心が欠けている人間にも見えない。
はすっぱな言葉遣いの割には、しっかり事態を見据える能力のある人物だ…と、ユキは好意すら覚えていた。
自分の意思で相手方に寝返った、もしくは意志すら持ち合わせていないし楽しい思いをさせてくれる相手ならいくらでも身を任せる…などという、同じ女性であることが汚らわしく思える人間…であるはずも無い。
ただ、男性を相手にする職業であろう…ということは、その方面にはとんと縁の無いユキにも、薄々気づかせる独特な匂いの様なものはあった。
「あんたと違って、あたしゃカタギじゃないから、気は随分楽なんだけどねー」
苦笑しつつ、ユキの、言葉にはしていなかった推測を認める。
本来なら、絶対に軽蔑してしまう所業を生業にする相手だというのに、嫌悪を感じないのは、この女性のしっかりした個性の為だろうか。
低俗さとは無縁の快活さがあった。
職業で人間を測るべきではないという見本か、それとも―――
(私も同じ場所迄、堕ちてしまったから―――)
「……それでも…やっぱり、辛いね…」
立場を同じにする、それだけではこの女性は、他人にこんな気弱な本音を漏らすことはあるまい、と思われる。
ユキにしてもそれは同様で、見境無くすがりつけるタチではない事を自覚している。
伊達に男と伍して働いてきた訳ではないのだ。
始めは、後れをとるまいと張った気も、いつしかその強さが身についてしまっていた。
同病相哀れむ、で、傷をなめあう趣味も無い。
今置かれている立場以上に共通するものを、お互いの中に感じた出会いであった。