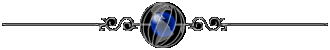
by くわはら智美
4.二人静
高熱を出したユキは、一週間、床から離れられなかった。
無理もあるまい。
翌朝、訪ねて来たゆかりに発見される迄、冷たい床に横たわり、シャワーを浴び続ければ、いくらそれが適度な温水であろうと。
雑菌が入り込んで化膿した傷口もある。
このありさまに、内藤医師も、今度は軽口を叩く余裕も無く、専門外の肺炎の治療に専念する。
そして、その間、アルフォンは一度も姿を見せなかった。
それを不審に思いつつも、医師もゆかりも、放心を続けるユキに問い質すことは出来なかった。
…ユキを見つけた状況から考えて、彼女に訊ねられるものでもなかった。
そして答えが返る由も…。
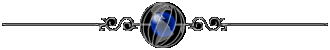
「森さん…」
ようやく三十七度台に迄熱の下がったユキに、医師が、遠慮がちに声をかけてみる。
「…例の検査の結果…あなたの推測通りでしたよ…」
反応は、無い。
熱の為か…と思っていた、いや、そう思いたかったこの放心状態は、何か別の理由で、心が焼き切れてしまったのだ…。
それを確認した医師は、大きく、ため息をつき、失望を吐き出す。
それこそ専門外だ。
閉ざされてしまった心の開き方など。
それが出来る存在は、恐らく、失われてしまっている。
…それも、いいかも知れない。
過ぎる試練を耐えて来たのだ。
もう、おやすみなさい。
優しく、娘に語りかける様に、無言で肩に置かれた暖かい手も、今のユキの心にほ届かなかった。
医師は一つ、間違っていた。
今のユキの目の前に古代が現われたとすれば、完全に彼女の心は破壊されたであろうから…。
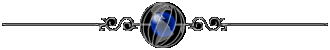
時間が無に帰した、澱んだ静寂を破ったのは、ゆかりであった。
荒々しくドアを開けたその手には、どこから持ち出したのか、果物ナイフが握られていた。
この家には、ユキの心理状態に対する配慮からか、凶器になりそうなものはあらかじめアルフォンの命で取り払われているはずだ。
…もっとも、ユキは、この自分にあてがわれた部屋と、そのバスルームしか知らず(もちろん、鍵をかけられた訳ではないが、好んでアルフォンの居る場所へ行くはずも無いし、居ない間に何か探ろうとしても無駄だということも判っていた)、この家の間取りすら知らなかった。
狂おしい熟を帯びた、焦点の定まらない瞳で、ベッドの上で動かぬ彫像と化しているユキを見つめ、意味のつかめないつぶやきを漏らしながら、ナイフを握りしめ、震える歩調で近づいていく。
「…この売女、殺してやるうっ!」
頭上に降りかざされた凶器の、冷ややかなきらめきも、ユキには無縁のものだった。
息急き切ってやっと追いっいた内藤医師が、ゆかりの身体ごと突き飛ばさなければ、ナイフはユキの頬をかすめるのではなく、胸に突き立っていただろう…。
「や…止めなさい…馬鹿な事は…」
初老の医師には過ぎる運動だったに違い無い、激しい呼吸を抑えて、やっと言葉を絞り出す。
「…人の男を取るなんて…この女…」
医師の言葉は耳をすり抜けるのか、枕を切り裂いたナイフにすら何の反応も示さないユキをにらみつけるゆかりの目は、異様に光り、すでに狂気を宿している。
「この人に一体何が出来るって云うんだね。冷静になりなさい」
医師の言葉が入り込む余地も無く、ゆかりの頭の中には、昨夜『自分の男』と交した言葉だけが渦巻いていた。
今では睦言を楽しむまでに、心を許した仲になっていたあの男と…。
『―――それで、どうしたのよ』
『アルフォンに云ってやったのだ。なかなかに気の強そうな、お前をてこずらせる程の女なら、一度試してみたいものだ…と。二度もケガをさせられおって、あやつ、それでも手放せないらしい。一夜だけならお貸し致しますが…などとはざきおる。余程気に入ったと見えるな…』
(この男が、ユキを抱きたがっている…?)
冷水を浴びせられた様に、一気にゆかりの身体の芯が冷えた。
『あれ程冷静だと思っていた男が、入れ込むなど…意外と女というものは危うい…と見える…』
後のつぶやきなど、ゆかりの耳には入っていなかった。
―――一度試してみたいものだ―――
―――一夜だけならお貸し致しますが―――
…一夜で十分だ。
この男の腕に他の女が抱かれるなど…。
気丈に振る舞い、ユキの身体の心配すらしていたゆかりだが、張り詰めたロープを渡るような精神状態に置かれていることには、ユキと変わりは無かった。
錯覚からか、本心か見分けのつけようが無いが、自分を凌辱した男を、深く愛している…という逆上しそうな自覚は、殺意の鉾先を、また一人の犠牲者の方へ向けさせた。
「あいつは…あたしだけのもんだ…誰にも渡さない…。たとえ機械じかけの人形だってかまわ…」
ゆかりの、熱に浮かされた言葉は、唐突に途切れ、スイッチの切れた人形の様に、ユキの上に崩れ落ちた。
はずみで再び、ユキの頬をナイフが傷つける。
その痛みと、ゆかりの身休の重さ、そして、戸口に仔む人影が、次第にユキを正気の世界へ引き戻して行った。
…忘れたくとも、忘れられない姿ではないか。
「…例え機械じかけの人形だとしても…とは、泣かせてくれるものだ…」
久々に聞く声は、ユキと初めて逢った頃の、氷の刃を取り戻しているかに思えた。
けだるげな仕草で、たった今ゆかりの脳天を貫いた銃を、医師の方へ向け直す。
…どこにそんな力と気力が残っていたのか…。
ゆかりの身体を押し退け、病人とは思えぬ素早い身のこなしで、ユキは、アルフォンと医師の間に立ち塞がっていた。
「ほ…う」
細められる目。
感心した事を表わす、低いつぶやき。
表面はほとんど変化は見られなかったが、アルフォンの内部は、歓喜に猛り狂っていた。
…戻って来た…。
私の愛した、飼い慣らされぬ野獣の睦が…。
瞳に射殺す力があれば…。
何も武器を持たないユキと、その瞳を向けられている当のアルフォンと…初めて二人の願いが重なった。
それを感じ取ってアルフォンは、至福の喜びに包まれた。
余りの事に動転している医師は、ただ、ユキの背とアルフォンとを見比べるばかりだった。
…とても、この二人の問に割り込めるものではない…それ程に厳しい対峙であった。
退け、とは云わぬ。
云って聞く相手なら、これ程までに愛するものか。
それに…それも目的の一つだろう。
しかし、この煉獄からの解放など、与えてやらぬ。
もがき苦しみながら、もっと私への憎しみを募らせていくがいい。
愛と錯覚する程に…。
もっと美しく爪を研ぐがいい…。
傷ついて血をしたたらせる程、強く輝くそのオーラで、私を焦がし、焼き尽くしてしまえ…。
永遠とも云える一瞬。
余人の入り込む余地の無い、視線だけの合歓…。
やがてアルフォンは、姿を現わした時と同様、フッと音も無く消え失せる様に退場した。
力が抜けたユキの身体が、へなへな…と崩れ落ち、あわてて医師が支える。
「…ゆかりさん…」
ふら…とゆれる様に身体が泳ぐのを支えながら、先程迄の力は一体どこから出て来たのか…と、医師は感嘆する。
支えてみれば、改めて彼女の小ささを実感し、頭が下がる思いだ。
後頭部に小さな丸い焦げた孔を開けたゆかりの身体は、アルフォンとユキの戦いの場の最後の客となって横たわっていた。
―――私を、殺しに来たのだろうに…。
この人も、そしてアルフォンも…。
軽く唇を噛む。
心が上手く、外界と接触出来ていなかった頃の事も、覚えている。
流れ込んで来る情報に、関心を払えなかっただけだ。
頬、そして首を伝う血が鎖骨にたまっていくなまあたたかい感触があった。
奇妙にもその傷は、ユキがアルフォンにつけた傷痕の位置と、酷似している。
誰にも渡さない…。
その狂おしい心を抱えて煩悶しているのは、ゆかりやアルフォンだけでなく、今、ユキも同じ激情に囚われていた。
誰にも渡さない。
アルフォン。
あなたは私が…この手で息の根を止めてみせる…。
医師が息をのむ。
親しくしていた人物の死体を前にしても、ほとんど感情を見せていなかったユキの…その、能面を思わせる顔に、次第に微笑が浮かぶ。
燃えさかる炎を閉じ込めた氷…。
ユキの微笑みは、アルフォンならずとも引き込まれる。
蟻地獄にも似た魔性を秘めたそれは、凄絶な迄に美しい…としか、表現出来なかった。
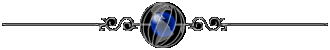
その日を境に、ユキと内藤医師の要は、消え失せた。
聞けば、ユキやゆかり同様にアルフォン連の『リポート』の為にぼろ屑のごとく扱われ、自殺を図っていた医師の一人娘が、その三日前に、一度は食い止めた命を衰弱の為に失っていた。
…だからこそ、医師はユキに強さを願ったのだろう。
一人では歩けそうもないユキを手助けして、『地下』の仲間達のもとへ駆け込んだか…。
それが判っていながら、アルフォンは、あとをつけさせるべく手を打たず、放置していた。
パルチザンを組織している反抗勢力。
その根城である地下都市への入り口は、アルフォン連の侵攻時に大多数は閉ざされ、あとは巧妙にカモフラージュされて、情報部の努力にもかかわらず、見つけだせなかった。
もっとも、さして気に病んでいた訳でもない。
全ては重核子爆弾の存在だけでこと足りる。
無駄な足掻きなど、出来ようはずも無いのだ。
ユキの立場からすれば、当然、地下都市へのルートを知っているだろう。
なのに、みすみすチャンスを見逃した上に、ゆかりの死体をユキと偽って処分していた。
上官は、ゆかりの事を監禁していた訳でもなく(事実、自由にアルフォンの屋敷にも出入りしていた)むしろ相手が居着いていた…位の意識しか無く、前夜に他の女の事を口にしたこともあり、嫌になって出て行ったんだろう、と、気にもとめていなかった。
あれ程のゆかりの想いは、かけらも届いていない…。
哀れなことだ、と、自分に似た境遇かも知れない女の最後を作り出した銃を手入れしながらアルフォンはほくそえんだ。
その銃口を、白く、細身の身体からは意外な程に豊満なユキの胸へあわせる姿を想像して。
実際、この豪快な大尉は、ゆかりどころに構っていられなかった。
女に情が移った…との報告や、痴情沙汰も何件か起こっていたが、先日は『心中』などをしでかしてくれた部下まで出てしまった。
軽目の脳みそでも悩まずにいられない。
セックスを楽しむのはいい。
しかし、女個人に―――しかも地球の―――いれあげるなどとは、何事なのだろう。
早速新しい女を調達し、『任務』に励んでいる大尉には、理解不能の感情だった。
「少尉、君も可成その女を気に入っていたようだが、まさか、私に取られると思って殺したのではあるまいな」
「…犬を処分したまでのこと…」
「お、そうだったな。軍関係者というのは、やはりいかんな。それも注意しておかねば」
…そうだ…こんな単純な男などに、判ってたまるか。
侮蔑を込めて自分を見やるアルフォンの視線にも気づかぬこんな男に、…こんな危うい感情の生まれる格好の土壌について解説してやったとて、理解は出来まい。
悪夢は、デリケートな感情を持つ者にだけ訪れると見える。
不公平と恨んで見ようか?
いや、私には感謝しか出来るはずも無い。
あの女と巡り合わせてくれた『宿命』というものに…。
種の衰えを気に病んでのこの出兵は、滅亡への秒読みを始めさせたのかも知れない・・・。
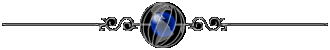
誰もが息を飲むような、鮮やかな首に残る手の跡を始めとした拷問と思われる生々しい傷痕を身体中にまとったユキが、無事に医師と共に地下のパルチザン組織に転げこんでから、一週間目が、決起の日だった。
傷も癒えきらず、体力も回復していないユキに、いつもの働きを求めるのは無理である。
しかし、そうと判っていても、兵力不足にほ目をつぶれるはずも無く、また、本人の希望も強すぎて、彼女をよく知る長官には、止められなかった。
…誰も、その傷の理由を問えなかった。
付き添っていた医師も、一言も触れなかった。
張り詰めたユキの周囲の空気に、誰もが口を閉ざした。
触れれば切れそうな迄に研ぎ澄まされたユキは、ただひたすら、決起の日を待ち望んでいた。
一度だけ、ユキの緊張が切れそうになった事があった。
ヤマトの存在と、古代の無事を知らされた時だ。
その一瞬こユキが見せた表情に、妙に長官の神経を引っ掻くものがあった。
…驚き、は、当たり前だろう。
安堵と喜びは、後に込み上げてきた涙が充分表わしていた。
…しかし、あの一瞬だけに見せた『絶望』としか表現出来そうにないユキの表情に、長官は不安を感じていた。
指揮をする立場では、無事でいてくれ…と願うしか無い。
同じもどかしさを抱えているであろう内藤医師と、無言で出発するユキの背を見送った。
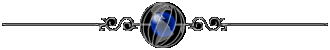
あの人が生きていた…。
そう聞かされて以来、ユキの心は、どんなに抑えつけようと、喜びに湧き躍っていた。
…そして、もう自分の死しか、望むものはなくなっていた。
何も他には…いや、ひとつだけ、アルフォンの首だ。
それをこの胸に抱けば、感涙を流しながら死ねるだろう。
サロメの気持ちが、過去にその役を演じたどんな名女優より理解出来る。
古代の生は、ユキにとって、地獄でしかなくなっていた。
好んで、最も危険なところへ飛び出していく。
仲間のパルチザン兵達もかばいきれないその無謀な動きは、確かに突破口を切り開いていたが、いつしか、乱戦の繰り広げられる場所から遠ざかっていた。
私のヨカナーン、どこ…。
自分はすでに正気を失っているのだろう。
戦場にアルフォンの姿を求め、彷徨っているなんて…。
そして、同じ思いに囚われたアルフォンと、『宿命』が最後の悪戯心を起こして、引き合わせた。
相手の姿を見つけても、驚きの色を見せること無く、二人は当然の様に銃を構えた。
しかし、体調が充分であっても、ユキはアルフォンの敵ではなかった。
対峙しているだけで、その事実はひしひしとユキを圧迫してくる。
スキが無さ過ぎる…。
ユキが唇を噛んだ時に、アルフォンが最初の引き金を引いた。
「あうっ!」
…地球に残された時に負った、一番の深手でまだ癒えきっていない左肩を貫かれる。
「はぅっ…」
次は右肩。
銃を取り落とし、地面に崩れ落ちるユキに、アルフォンは次々と、無表情に銃のエネルギーを打ち込み続ける。
試し撃ちの標的だとでも思っているのだろうか…。
右足、左足、それぞれの大腿部と太腿、そして膝。
左の肘。
エネルギーは、あらかじめ弱くしぼってあるらしく、貫通するだけで致命傷にはならなかった。
が、撃ち込まれる度に、ユキのしなやかな身体には激痛が駆け抜け、ばねじかけの人形の様にのたうちまわった。
早く殺してくれ…なんて云わない。
古代が、自分がアルフォンとしてきた事を知る前に死ねるのなら、この瞬間も、至福への階段を昇っているにすぎない。
アルフォンに撃たれることに恍惚すら感じて居た。
右胸に、灼熱を感じた。
何度もこの男になめまわされた胸など、惜しくも無い。
…それでも…ほとんど動かない手と足を引きずって、自分は何をしようとしているのか…。
ユキ自身、説明などつけられない行動。
しいて云えば、この男にだけは、息の止まる瞬間まで抗い続けてみせる。
こんな事位で負けを認めるくらいなら、始めから這いつくばってアルフォンの情婦に堕ちてやっただろう。
右肘だけで、自分が取り落とした銃へ向けて、這いずって行く姿を、アルフォンはただ黙ってながめていた。
アルフォンの愛したその瞳は見えない。
しかし、この、のたうちまわる姿も、うっとりと見惚れる程に美しいものではないか。
足掻くがいい。
最後まで私に抵抗しろ。
服従など許さない。
動かない表情の下は、極限の愛情に煮えたぎっていた。
すぐ目の前だというのに、ほんの一歩の距離だというのに、何と遠いのだろう。
…次は、左胸だろう。
早く、早く…。
ベッドの上でアルフォンを求めた様に、今、自分に撃ち込まれるべき別の形のエネルギーを、ユキは待ち焦がれていた。
行為と思考は、全く噛み合っていない。
…あれ程にアルフォンを憎みながら身体が求め続けた頃とは反対に、今、心が渇望し、身体は無意識のままに抵抗を続けていた。
…いや、身体中に作られた新たな傷の痛みからか、心も混沌に包まれて、まともな思考をなしえていなかった。
今自分はどこにいるのか?
何度も夜を重ねたベッドの上か、それともあのシャワー室で首を絞められながら見ている幻だろうか…。
銃に辿り着いたユキは、震える手で、何とか拾い上げた。
次の瞬間、ユキの右手にアルフォンの手が添えられ、たがえる事無く正確にサイボーグの身体の数少ない急所―――厳重に保護された動力炉からわずかに逸れた、エネルギー伝導ケーブルにあたる―――に据えられる。
訳が判らないまま、条件反射で引き金を引いてしまったユキの体に、致命傷を受けたアルフォンが崩れ落ちて来る。
「…アル…フォン…?」
一体何が起こったというのだ。
自分へのとどめは、一体どうしたのだろうか。
ぼんやりと慣れた身体を抱き抱えながら考えるユキの目の前に、一枚のディスクが差し出された。
「…重核子爆弾のデータだ…」
苦しげなアルフォンの声…。
急速に生命が失われつつある姿に、ユキは我に返った。
「…死ねまい…? これを手に入れては…」
この男は…自分に地獄の中で生きろと云うのか。
どこまで憎ませれば気がすむのだろうか。
…やっと解放される…それをこの男が与えてくれると思うからこそ、サディスティックな仕打ちも、古代を裏切ってしまった自分への報いだ…と、受け入れられたものを…。
…お前を喜ばせる為に、自分は抵抗を続けたのではない…!
怒りと驚愕に目を見張った時、ふとアルフォンが、弱々しく微笑んだ。
アルフォンは確かに満足していた。
見えない古代という存在に、妖妬に狂いもしたが、こうして確実に、ユキの心の一部を切り取り、手に入れる事が出来たのだ。
自分達の種族の未来に関する引導など、自分が手に入れたものの代価としては安すぎはしまいか?
ユキが味方にこのデータをもたらせるか、その前に命が尽きるか…五分五分というところだろう。
「…美しい…。狂おしい怒りに問えるお前が…一番美しい…」
これ以上この男の戯言など、聞きたくもない。
ユキは、自由にならない身体を何とか動かし、ディスクをアルフォンの手から引き取り、すでに視力を失っている様なアルフォンを見下ろす。
この世で一番美しいと思うものを日に焼き付けて死んで行けるのは、幸福と云えるだろう。
そして、忘れられるはずもないしるしをつけて、それを抱えたままユキに、修羅の中を生きて行けと云う、この世で一番、憎んでいる男…。
ユキの記憶に残る事こそ、アルフォンの最大の幸福かも知れない。
「…忘れてやるわ…あんたなんか。図太く生きてやる。女は遷しいんだから…」
私はあんたなんかに負けやしない。
ユキの言葉が聞こえたのか、アルフォンの唇が微かに動く。
「それでこそ」と読み取れた動きを、ユキは、自分の唇でふさいだ。
…確かにユキはアルフォンを憎悪していた。
しかし、それと同じ位の強さで、愛してもいた。
完全にアルフォンの唇から生命の名残が消えるまでくちづけを続けたユキの頬には、涙が流れ、そしてそれが乾いた跡があった。
そして、味方の姿を求めて、瓦礫の中を這いずり始めた。
Fin