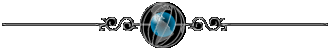
by くわはら智美
2.ヘルプ・ミー
長官に提出した辞表は、預かり、という形にされてしまった。
仕方無い…か。
自分の様に便利さを既に実証して来た人間が、そう簡単に解放してもらえるとは思えない。
ましてや、戦後復興という目前の大仕事が控えているのだ。
人材を一人でも遊ばせておく余裕は無いだろう。
それでも、だ。
判っていても、自分にとって今一番重要なのは、全人類への福祉より、ボロボロに傷ついた恋人だった。
過去にも選択の機会はあった。
が、岐路に立った事を意識する以前に古代は、『したいこと』ではなく、『すべきこと』を選び取ってきた。
しかし今は、暗黒星団帝国に傷つけられた人々や街の為に働くことより、少しずつ目覚める間隔の短くなっていく(それでも、日に一度、あるかないか…というところだが)ユキの視線を捕らえる方が、古代には大事な事だった。
周囲が慌ただしく動いている中、何もせずにただひたすら待ち続けるだけの日々は、貧乏症を自覚している古代には可成辛いものだったが、ユキを一人きりにしてしまえば、また後悔に襲われるのは必至だった。
後ろめたさを捩じ伏せてでも、今回ばかりは心の望むままに…と、古代は、病院の無為な客となっていた。
天敵の参謀あたりは、さぞかし怒り狂っていることだろう…と想像はつく。
だが、自分は平時でも、あの、人のあら捜ししか出来ない人間よりは余程役立ってきたはずだ、とも思ってしまう。
思い上がりでも何でも無い、お前は十分に働き続けてきたから、今はユキの為に行動する事も許される、と、誰かに云って欲しい…。
判っていても、甘えが出る。
古代も十分に疲れ、傷ついていた。
ユキの為だけでなく、己れの心を癒す為にも必要な休息だった。
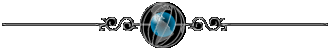
看護婦とは、想像以上に大変な仕事だ…と、古代は感心していた。
ユキの仕事を見ていて、判ってはいたつもりだったが、間近で見続け、手伝ってみると実感として伝わって来る。
やはり、貧乏症という不治の病には勝てず、ユキが当分目を覚ましそうにない頃を見計らって、親しくなった看護婦の手伝いを始めた古代に、訪れた真田や島達は苦笑していた。
看護士用の白衣を貸してもらった古代の姿に、「似合うぞ」という言葉が思わず出てしまう。
相手が意に介さなければ、皮肉にもならない。
…実際、古代にはその姿の方が似合っているように、『昔の姿』を彼の兄から問いて知っている真田などには特に強く感じられてしまう。
人を世話する穏やかな表情は、自然だった。
時折、『休暇中』の古代のサインを必要とする書類等を持って見舞いに訪れてくれる彼らに、古代は感謝していた。
自分の抜けた穴を埋め、我が儘を許してくれる彼らは、古代が無意識に求めている『甘えられる存在』でこそないが、頼れる仲間であることは確かだ。
今日訪れたのは、島一人だった。
差し当たり用事も無いので、中庭を当てもなくふらふらしてみる。
古代が辞表を出して自主的に休暇状態に入ってしまって、そろそろ二ケ月がたつ。
ユキの容態は可成落ち着き、生命の危険は去り、じりじりとした焦りを感じさせる歩みではあるが、着実に回復に向かっていた。
しかし、古代の扱いを休暇にしておける限度も越えていた。
「あてはまる様な休業の条項も無いしなあ…」
長官から相談して来るように云われたが、半分は『説得』だろう、と、島は思う。
島にしても、ひたすらユキの身体の心配を続けるだけの生活が、古代の精神衛生に良いとも思えないので、復職して、以前の様に活躍する方が、ユキも安心するのでは…と考える事もある。
が、古代をそっとしておいてやりたいのもまた事実だった。
帰りの旅で見せた様な危うさは、今は無いが…。
「辞めさせては、もらえないのかな…」
表情から、鋭さが消えた…。
そんな印象を受ける柔らかい微笑みを浮かべ、何となく空を仰ぎ、うるさげに前髪をかきあげる。
こんな仕草は、見慣れたものだったが、自分が知っている古代という人物は、訓練学校で知りあってからの彼でしかない。
出会う以前…どんな少年だったか。
今の古代の表情は、それを物語っているようだった。
この古代に、軍の仕事は出来ないな…。
そんなことまで感じさせてしまう。
能力の問題ではない。
老人から感謝されて浮かべる古代の表情は、それだけ自然だった。
淋しさも確かに感じるが、あんな危うげな古代を見るのはもうごめんだ…と、そちらの気持ちの方が確実に大きい。
古代は、自分から、戦ってきた日々を意識して忘れようとした訳ではない。
傷ついたユキの心を受け止められる様に…と、穏やかでおおらかな精神状態を保てるよう努力してきた結果だった。
それが自然と、昔の自分を取り戻していく行為に似てしまうことに、古代は奇妙な途惑いも感じていた。
「まだ、もう少し意識がはっきりしないそうだな」
島が、ユキの様子の方に話題を切り替える。
「ああ。俺のことは判ってるようだけど、自分がどうして負傷したか、といったことまでは思い出せない…と云うより、そこまで思考がまとめられないんだ。その前にまた、意識が沈んでしまう…」
「で、ポケットベルに呼び出されてかけつけ、せいぜい一分のご対面に命を賭けてる…って訳か」
古代の胸ポケットの小さな機械を指さし、おどけた口調で島が揶揄する。
このポケットベルは、ユキの脳波を検出する装置に連動し、意識を覚ましかけたら知らせるようになっていた。
「そんな状態で大丈夫なのか?」
「これでも随分と良くなって来ているんだぞ」
さりげなく恐ろしいことを云うもんだ…と、島は小さく肩をすくめる。
佐渡が、最初の頃のユキを見て『何がユキの生命を繋ぎ止めてるのか、想像もつかん』と、わざと呆れた様に呟いた言葉を思いだした。
片肺をやられたこともあり、まだ呼吸すら機械の手助けを得てようやくしている…。
ユキがそんな状態に陥った原因というか、過程を知る人物から、古代は詳細を知らされているらしい。
その上で軍を辞め、ユキの側にいることを選ぶというなら、古代の望む通りにさせてやりたい。
古代とて、自分が置かれている立場をわきまえているはずだ。
それでもなお…という、古代の、柔らかな態度と裏腹にきっぱりとした決意を見せられると、自分には無理強いの言葉は出せない。
やはり自分は説得役として適任ではないな…と島は内心苦笑する。
そんな役目は、ニヶ月前の古代の様子を知らない、無神経な奴でなければつとまらないだろう。
あの頃の古代の、笑っていながら虚ろな目が、島は怖かった。
二人を包み込んだ沈黙を、小さな電子音が、遠慮がちにくぐもった音で破った。
ポケットから取り出し、「…早いな…」とっぶやきながらスイッチを切った古代は、島にうなずいて見せてから、ユキの病室へ向けてかけだした。
足音を立てない素早い身のこなしは、島の見慣れた、訓練され、身についてしまったものだった。
病室の手前で呼吸を整え、静かにドアを開ける。
ICUの頃と違って無菌状態に気を使う必要がなくなったおかげで、古代も気軽に外に出られるようになった訳だが、身体の回復に、意識の方がどうも遅れがちに見えることは、島に云われる迄もなく、気がかりだった。
続いて島が緊張した面持ちでドアの隙間から身体を滑り込ませる。
何度か見舞いに訪れていたが、ユキが目を覚ましているところにでくわしたのは、これが初めてだった。
左腕の無い痛々しい姿は、なかなか慣れる事は出来ないな…と、どうしてもその部分から目を逸らしてしまう島は、慣れという以上に、ありのままのユキの姿を自然に受け入れている古代に舌を巻く思いだった。
病院側も、思い出した様な目覚めを繰り返すだけのユキの状態にいちいち対処出来ないので、古代に任せきりのようだ。
据え付けられた機器がユキの病状を刻々と報告してくるし、急変でもしない限り、特別な治療の必要も無い。
「…ユキ…」
虚ろに見開かれていたユキの瞳が、声の方へ視線を移し、古代の婆を捉えた。
わずかに目が生気を取り戻し、微笑んだように見える。
ただ、古代の存在を確認して、また眠りに戻る。
おとぎ話の姫君の様だ…と、島は妙な感心をしてしまう。
あの話の姫君ならば、確か、王子がくちづけをすれば魔法が解けるほずだが、彼女の場合はそう簡単に事が運ばないからこいつも苦労している訳だが…と、必死でユキを見つめる古代の横顔をながめる。
随分、こんな無邪気な喜びの表情など見ていなかったな…と。
その古代の表情が、一瞬、緊張に引き締まった。
酸素マスクに覆われたユキの唇が、微かに動いたのだ。
それが、初めてのことだ…というのは、古代の反応を見ればよく判る。
島も思わず身構えてしまう。
何か話そうとしている…が、声は全く聞こえない。
例えしぼり出したとしても、マスクのせいでこもってしまって聞こえにくいものになるだろうが、もとより声を出す力も失われているようだ。
それでも確かに、『古代くん』という言葉は読み取れた。
しかし、何とユキの幸福そうなことか…。
彼女も、重い屈託を抱えていた。
自分自身が戦い続けなければならない苦しさに加えて、戦うごとに精神を削り取られていくような古代の様子に、誰よりも心を痛めていたのは彼女だった。
そんなことはすべて忘れ、自分が生命の危機にさらされるような傷を受けたことにも気づかず、ただ、古代の姿に喜ぶ無垢な微笑み…。
生まれたての赤ん坊でもなければ出来ない表情だろう…と、いつかの土門少年と同じことを島も考えていた。
が、いきなりそのユキの表情が凍りついた。
余りの唐突な変化に、古代も島も反応を決めかねて途惑うばかりだ。
撃たれた時のことでも思い出したのだろうか。
しかし、それならば、恐怖と苦痛…といったところだろう。
なのに、このユキの驚愕に凍りついた表情に含まれるものは、明らかにそれ以外の…あえて表現するならば、絶望と憎しみ、だろうか…。
そして、またもいきなり変化は起こった。
ユキが、口許を覆っているマスクをもぎ取ったのだ。
右腕につけられていたコードが急な動きについていけず、機械や腕からはずれて宙を舞うのを、ただ島は呆気に取られて見ていた。
…まさか、このユキが動けるとは、目にした今でも信じ難い。
ユキの表情が、苦しさに歪む。
咳き込む力も無いようだ。
今の急激な反応で今度こそ力を使い果たして、ぐったりしてしまう。
あの表情は、息苦しさと、心の苦しさと、どちらがより多く占めているんだろう…とぼんやり考える島は、古代の叫びで我に返った。
「ユキッ! 何てことを!」
酸素マスクのホースは引きちぎられ、用を為さなくなっている。
片肺が傷つけられ、衰弱の為に自発呼吸では充分に酸素を取り入れられない状態のユキにとって、これはまさしく自殺行為だった。
―――自殺?
まさか、と大きく首を振った島は、ともかく、病院のスタッフに知らせよう、と、ドアへ向かう。
異変はナースセンターへ、機器から直接報告が入っているだろうが、この場合、自分に出来ることといえば、見たことを説明することだけだろう。
部屋を出る寸前に振り返った島は、ユキにくちづけて、人工呼吸をする古代の背を見た。
こんな場合の正しい処置の仕方など、古代にも島にも判るはずはなかった。
だが、何かをせずにいられないのも確かだろう。
―――ユキ、眠り姫なら、王子様にキスされたら起きるもんだぞ!
悔しい!と、心の中で島は叫ぶ。
何に対してかは判らないし、今、目の前で起こったことが一体何だったのか、と考えをまとめる余裕も無い。
ただ、無性に悔しく、喚き出したい歯がゆさを抑えつけて、ドアを閉じ、慌ただしい足音が近づく方へ駆け出した。
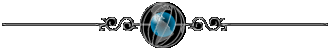
処置を待つ間、古代と島は、所在無捌こ廊下に立ち尽くしていた。
待合所のソファに座る気も起きずに、ただ無言で、時折看護婦が出入りする度に、わずかに顔を上げるだけという、同じ反応をしていた。
違っているのは、古代はユキの病室のドアの斜め向かいの壁に背を預け、目を伏せているのに対して、島は、その古代をひたすら凝視しているところだ。
「…古代さん」
主任のバッジをつけた看護婦が、声をかけながら歩み寄ってくる。
「もう大丈夫です。落ち着きましたよ。…ただ、今日はもう、面会は遠慮していただけますか?」
年配のベテラン看護婦の、見るものを安心させる信頼感に満ちた笑顔に、青白くこおばっていた古代の表情がわずかにゆるんだ。
情けない、とも云えそうな古代の頼り無げな様子に、こいつにも手当が必要なんじゃないか…と島は危ぶむ。
「ありがとうございました」
「でも…びっくりしたわね。気をつけてあげてね」
「はい…」
一体何が起こったのか…と、深く追及してこないのは、古代の様子を見兼ねたのであろう。
…それとも、この看護婦も事情を知っているのだろうか…?
島は、自分もそれにたどりついたことを確信していた。
「古代…」
看護婦を見送った古代が、ゆら…と振り返る。
…幽鬼とは、こういうものではないだろうかと鼻白みながら、古代の青ざめた顔を見据えて、言葉を吐き出した。
「…嘘だろう…?」
どうか嘘だと云ってくれ!
自分も、古代と似た顔をしているのかも知れないな…と思いつつ、これは、確認の為の問いでしかないことも知っていた。
あれはまさしく、絶望にかられた人間の、発作的な自殺の衝動に他ならなかった。
ユキが自殺を図る…。
そんな馬鹿なことがあっていいはずない。
ユキの、風を受け流す柳のような勃さを、島は知っている。
信じている。
が、現実に起こった以上、原因が存在する。
そうそう思いつくはずも無いが、ユキでさえもそうしたくなる程のものも確かにいくつか思いつける。
例えば、古代が目の前で死んだりすれば…。
そして、いくつかの候補の中から、消去法で振るい落して行けば…残るものは一つだった。
そんなことに負ける彼女ではないはずだ。
しかし、混濁した意識がはっきりした瞬間の衝動だとすれば…。
古代は、ずっとこれを恐れ続け、側についていたのか…と、今更ユキが重核子爆弾のデータを得られたというその理由に思い当たる。
「…今のは、まだ、はっきりものを考える力が戻っていないから、あんなことをしたんだろう…。ユキが冷静になって、身体も自由に動かせるようになった時の方が…怖いな…」
投げやりにつぶやく古代の、無責任な口調に、思わず怒りが込み上げる。
「ユキは、あんなことを繰り返す人間じゃ無い!」
「お前はユキじゃない! …女性ですらないんだ、俺たちは!」
穏やかな仮面の下に押さえこんでいた古代の激情が爆発した。
一瞬、島をにらみつけた古代の表情は、ユキを信じたいのに、愛しているからこそ最悪の事態ばかりに思考をめぐらせてしまう。
苦しさに歪み…今にも泣き出しそうな子供にすら見えてくる。
…もしかしてユキは、『女』を武器にしたのだろうか。
そうならば、『狂犬に噛まれた』という使い古された云いまわしで、彼女自身が納得出来ないものがあるだろう。
だからこそ古代も、不安を大きくしているのだろうか。
風雪に耐える柳も、落雷に裂けることもある…。
いや、自分が憶測にいたずらを拡げるのはよそう、と、島は、迷路に入り込んでしまいそうな自分の思考に歯止めをかけた。
…先にその危険な地帯に踏み込んでしまった古代の為にも、自分は踏み留まらなければならない。
恐れていたことが現実になり、必死に耐えてきた不安に押しつぶされそうになっているこの古代の為に…。
古代の背が力無く壁をすべり降り、腕で頭を抱え込み、うずくまる格好になってしまう。
何の解決にもならないと知っていても、途方に暮れて座りこむことしか、今の古代には出来ない。
こんな時でも涙は失われたままの自分が、古代は不思議だった。
「…真田さんと、佐渡先生に話してもいいか?」
弾かれた様に顔を上げる。
瞳は、訳の判らない状態に突き落されて怯える子供そのものだった。
「…い、嫌だ。駄目だ、そんなこと…」
「俺は知ってしまった。もう忘れることは出来ないんだ!」
舌うちを辛うじて押さえて島は叫ぶ。
人気の無い廊下に、残響が、断定した語尾を振り返す。
知って…覚悟していたはずの奴が、こうも取り乱すとは…。
それだけ、大きな存在だということだろう。
古代にとっては、今や、最後に残されたもの…かも知れない。
宝物を取り上げられた子供じゃあるまいし、こんな不甲斐無い姿など、初めてで、二度とごめん…という代物だ。
古代にすがる様な目なんか向けられても、嬉しくとも何ともないんだよっ!と、島は心中で毒づく。
「誰が一番辛いか、考えるまでもないだろーがっ!」
不甲斐無さ過ぎる姿に苛立ち、しっかりしろ!と、座ったままの古代の頭を、やや乱暴にはたく。
誰が…などというのは、云われる迄も無く判っているはずだ。
それでも、他人に云ってもらわなければ動き出せない時もある。
今の古代がまさしくそれだった。
気休めに過ぎないと判っていても、誰かに甘え、励ましてもらいたい。
ユキの意識が回復した以上、今迄執行猶予されていたことに正面から対峙しなければならなくなる。
足をすくませて立ちつくすことは許されない…と、誰かに背中を押し出して欲しかったのだ。
徐々に古代の表情が、落ち着きを取り戻していくのを見て、島は安心した。
最初のパニック状態さえ脱せば、古代は大丈夫だ。
これ以上泣き言を続けるような奴が、あれ程の戦塵の中を歩いてこれたはずが無い。
夢から覚めた様な表情で、古代は、小さなため息をついた。
「すまない」と、小さくつぶやいた後、抱え込んだ膝の上に顔を埋める。
やがて、勢いよく顔を上げて立ち上がった。
島の手を借りたりせずに、一人で立ち上がらなければならないと思い定めた様に。
表情には、決意の厳しさは無く、ごく自然な快活さがあった。
それを確認して島は、先程古代がうろたえた申し出を、もう一度してみた。
「…真田さん達に…?」
気乗りしない様子で口ごもる。
本来なら、島にも知られたくは無かったと思っているから、当然だろう。
だが、島の方は、『毒を食らわば皿まで』という諺を古代に思い知らせてやるつもりだった。
…諺の用い方が違う気もするが、細かいことはこの際気にしない。
「現実問題を考えろ! 少しは蓄えもあるにせよ、軍を辞めて、どうやって食ってく気だ。―――ユキから目を離せる状態じゃ
ないだろうが」
確かにそうだが…話が見えない。
「ユキは退職…って、これは仕方無いな。年金もいくらかは出るだろう。…褒賞金でも出してもらいたいところだな。問題はお前だ。何とかして休暇扱いにして、給料の何分の一かでも出させてやる。…まさか、産休や育児休業は無理だが…」
「…おーい」
一人で盛り上がる島に、目を点にして古代が呼び掛ける。
「俺達が手足になって動くから、お前は心置きなくユキに貼り付いてろ」
「島…」
「フォローは完壁にしてやる」
きっぱりと云いきった。
…その為に、真田達に…という訳か。
実際、最低限、あの二人には打ち明けずに済みそうにないし、隠しおおせられるとも思えない。
充分に動くには必要だろう…ということも納得出来た。
ユキと、そして自分の為に、出来得る限りのことをして見せると云ってくれているのだ。
申し訳無さで辞退している場合では、確かにない。
現実面では、手を差し延べられるが、ユキの、そして自分の精神面を支えられるのは、お前だけなんだぞ、と云い渡されてし
まったな…と、古代は苦笑しつつ、肩をすくめてみせた。
「…任せるよ」
古代の言葉にうなずいた島は、改めてユキの眠る部屋の方を振り返る。
「…長い…戦いになりそうだな…」
「ああ…」
必ず勝ち抜いて見せる、と、決意を込めて古代もそのドアを見つめた。
そして、眠りの中でしか安らぐことの出来ないユキの為に、その夢が悪しきものでないことを…と願ってみる。
…そしてふと、おかしくなった。
誰に向かって祈るのか。
神などいるはずが無い。
いるとすれば、どうして彼女だけをこれ程に苦しめるのか。
それ程の罪が彼女にあるというのか?
自分にならば…あるだろう。
だが、それを彼女が代わって受けているなど…それを決めた『神』が目の前にいれば、半殺しじゃ気が済まないぞ、と、物騒な
思いを抱く自分がおかしく、微かに笑った。
次のページへ
前のページへ
『愛撫への扉』ページへ戻る
メニューページへ戻る